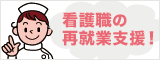第4章第2項2(海草圏域)
〈海草圏域〉
【構成市町村】 海南市、紀美野町
【面積】 229.40キロ平方メートル
【人口】 54,026人(令和5年4月1日現在)
【高齢化率】 38.9%(令和5年1月1日現在)
(1)圏域内の障害者手帳交付状況(令和5年3月31日現在。上段:人、下段:構成比)
身体障害者手帳
|
視覚障害 |
聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく |
肢体不自由 |
内部障害 |
合計 |
|
196人 |
474人 |
1,801人 |
1,053人 |
3,524人 |
|
5.6% |
13.4% |
51.1% |
29.9% |
100.0% |
療育手帳
|
A1 |
A2 |
B1 |
B2 |
合計 |
|
98人 |
99人 |
155人 |
276人 |
628人 |
|
15.6% |
15.8% |
24.7% |
43.9% |
100.0% |
精神障害者保健福祉手帳
|
1級 |
2級 |
3級 |
合計 |
|
73人 |
338人 |
373人 |
784人 |
|
9.3% |
43.1% |
47.6% |
100.0% |
(2)障害福祉サービス等の見込量(1か月あたり)
〇訪問系サービス(1か月当たり)
|
種類 |
単位 |
令和5年度 実績見込 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|
居宅介護 |
時間 |
2,389 |
2,830 |
2,920 |
3,010 |
|
人 |
126 |
148 |
154 |
160 |
|
|
重度訪問介護 |
時間 |
0 |
30 |
30 |
50 |
|
人 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
|
同行援護 |
時間 |
79 |
102 |
102 |
102 |
|
人 |
8 |
13 |
13 |
13 |
|
|
行動援護 |
時間 |
57 |
50 |
50 |
50 |
|
人 |
7 |
3 |
3 |
3 |
|
|
重度障害者等包括支援 |
時間 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
人 |
0 |
0 |
0 |
0 |
〇日中活動系サービス(1か月当たり)
|
種類 |
単位 |
令和5年度 実績見込 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|
生活介護 |
人日分 |
ー |
3,191 |
3,240 |
3,289 |
|
人 |
221 |
235 |
249 |
263 |
|
|
自立訓練(機能訓練) |
人日分 |
0 |
25 |
25 |
25 |
|
人 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
|
自立訓練(生活訓練) |
人日分 |
192 |
194 |
200 |
226 |
|
人 |
13 |
13 |
14 |
16 |
|
|
就労選択支援 |
人 |
ー |
ー |
2 |
3 |
|
就労移行支援 |
人日分 |
156 |
205 |
210 |
235 |
|
人 |
9 |
12 |
13 |
15 |
|
|
就労継続支援(A型) |
人日分 |
ー |
780 |
800 |
820 |
|
人 |
35 |
58 |
82 |
106 |
|
|
就労継続支援(B型) |
人日分 |
ー |
4,370 |
4,430 |
4,490 |
|
人 |
277 |
337 |
382 |
406 |
|
|
就労定着支援 |
人 |
3 |
10 |
11 |
12 |
|
療養介護 |
人 |
22 |
23 |
23 |
23 |
|
短期入所(福祉型) |
人日分 |
139 |
178 |
185 |
210 |
|
人 |
17 |
15 |
16 |
18 |
|
|
短期入所(医療型) |
人日分 |
32 |
23 |
25 |
27 |
|
人 |
7 |
4 |
5 |
6 |
〇居住系サービス(1か月当たり)
|
種類 |
単位 |
令和5年度 実績見込 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|
自立生活援助 |
人 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
共同生活援助 |
人 |
112 |
132 |
138 |
144 |
〇相談支援(1か月当たり)
|
種類 |
単位 |
令和5年度 実績見込 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|
計画相談支援 |
人 |
161 |
165 |
176 |
187 |
|
地域移行支援 |
人 |
4 |
6 |
7 |
9 |
|
地域定着支援 |
人 |
1 |
4 |
5 |
7 |
〇障害児通所支援(1か月当たり)
|
種類 |
単位 |
令和5年度 実績見込 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|
児童発達支援 |
人日分 |
730 |
796 |
816 |
836 |
|
人 |
59 |
63 |
67 |
71 |
|
|
放課後等デイサービス |
人日分 |
1,327 |
1,230 |
1,280 |
1,330 |
|
人 |
115 |
135 |
141 |
147 |
|
|
保育所等訪問支援 |
人日分 |
2 |
6 |
7 |
13 |
|
人 |
2 |
2 |
3 |
4 |
|
|
居宅訪問型児童発達支援 |
人日分 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
人 |
0 |
1 |
2 |
2 |
〇障害児相談支援(1か月当たり)
|
種類 |
単位 |
令和5年度 実績見込 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|
障害児相談支援 |
人 |
62 |
50 |
56 |
62 |
〇市町村における医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置
|
種類 |
単位 |
令和5年度 実績見込 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|
コーディネーターの配置人数 |
人 |
1 |
1 |
1 |
1 |
〇精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
|
種類 |
単位 |
令和5年度 実績見込 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|
精神障害者の地域移行支援 |
人 |
ー |
6 |
7 |
8 |
|
精神障害者の地域定着支援 |
人 |
ー |
4 |
5 |
6 |
|
精神障害者の共同生活援助 |
人 |
ー |
36 |
41 |
46 |
|
精神障害者の自立生活援助 |
人 |
ー |
4 |
5 |
6 |
|
精神障害者の自立訓練(生活訓練) |
人 |
ー |
2 |
3 |
4 |
(3)海草圏域の主な取組
〔地域生活支援体制の充実〕
- 障害のある人が高齢になっても住み慣れた地域社会で生活できるよう、介護保険制度における居宅サービス事業者に訪問系サービスへの参入を働きかけ、在宅サービスの確保に努めます。また、障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、事業者等関係機関と連携し、緊急時の受入体制を整備しました。また今後、運用状況の検証を行い受入体制の見直しを行います。
〔相談支援体制の充実〕
- 基幹相談支援センターを中心とした相談支援体制を整備し、基幹相談支援センター、委託相談支援センターの役割を明確にするとともに、自立支援協議会との連携により、支援方針の共有や地域の支援体制の構築を図るとともに、相談業務を担う人材の育成や資質の向上を図ります。
〔障害のあるこどもに対する支援〕
- 市町の乳幼児健診や保育所等の健診、保健所の発達相談による早期発見の他、専門医療機関、障害児者サポートセンター及び発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、発達障害のある児や疑いのある児とその家族への総合的な支援を早期に行います。また、令和8年度末までに、圏域内に未設置の児童発達支援センターの開設の実現を目指します。
〔就労支援体制の充実・促進〕
- 自立支援協議会に設置している「就労部会」において、就労アセスメントシートを活用した支援や、インターンシップ等の就労体験による就労を実施し、一般就労につなげていきます。また、共同受注窓口を設置し情報発信を行うとともに、各種イベント等による移動販売等により工賃の向上につなげます。
〔精神障害のある人の地域生活支援体制の充実〕
- 保健、医療、福祉関係者が情報共有や連携を行い、精神障害のある人が地域で安定した生活を継続していけるように地域包括ケアシステムの構築を進めます。また、精神障害のある人の日常生活や就労を支援するため、精神保健福祉士等の職員を配置した地域活動支援センターの設置を目指します。
〔社会参加の環境づくり〕
- 障害への理解だけでなく、障害のある人を取り巻く社会的障壁を取り除き、障害のある人もない人も地域の一員として生活できる社会の実現を図るため、障害者団体と連携して啓発活動を続けて行います。また、障害者団体と連携して学校等を巡回し、障害について学ぶ機会を設け、心のバリアフリー化に取り組みます。